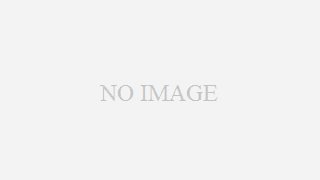杉江松恋
一覧
杉江の読書 キット・リード『ドロシアの虎』(サンリオSF文庫)
中村融編の〈奇妙な味〉アンソロジー、『夜の夢見の川』(創元SF文庫)に収録された「お待ち」があまりに強烈だったもので、キット・リード作品をもっと読みたいと思った。 リードは1932年生まれで、ジャーナリスト出身の作家である。二桁に届く長篇があるのだが、邦訳は『ドロシアの虎』(友枝康子訳/サンリオSF文庫)しかない(注:細谷正充さんの指摘で気づいたのだが...
落語本の話をしませんか
本日8月21日、「『落語の入り口』の入り口」と題しまして、落語本について語り合う読書会&懇親会を企画しております。出演者は新作落語作家である井上新五郎正隆さんと杉江松恋です。読書会とはいうものの、入り口で二人がお気に入り落語本のガイダンスをして、その後はめいめいが好きな書名を挙げながら好きに話をするという形式ですので、どうぞお気軽にご参加ください。落語本の出...
杉江の読書 第157回直木賞について 20170719
続いて直木賞である。 木下昌輝『敵の名は、宮本武蔵』(角川書店)は、剣豪と敵対して剣を交えた者たちを主人公とし、彼らの視点から宮本武蔵という人物を浮かび上がらせていくという形式の作品だ。木下にはデビュー作であり最初の直木賞候補作となった『宇喜多の捨て嫁』や『戦国24時 さいごの刻』などオムニバス形式をとった作品が多数ある。ミステリーで用い...
杉江の読書 第157回芥川賞について 20170719
今回の芥川賞・直木賞には、軸がはっきりと見える候補作が揃った。 芥川賞のそれは、社会の多様性を小説はいかに描きうるかということに尽きる。今さら言葉を重ねるまでもないが、現代を支配するのは不寛容を基調とする空気だ。たとえば倫理観においては、これほどまでに清潔さが重視され、自分勝手であることが忌まわしいものと批判される時代はかつてなかったように思う。同じ鋳...
電撃座通信 若手精選「らくご甲子園2017」のお知らせ
八月のお盆期間中、新宿の小さな演芸会場・マイクロシアター電撃座は一つの挑戦に踏み出します。 これまでお付き合いがなかった、もしくは客演をお願いしたことはあってもまだ会を開いたことはない二ツ目の落語家さんにお声掛けをしました。暑い盛りですが落語界の将来を担う若手の競演はかなり熱いです。一週間で六名、将来が楽しみな二ツ目が日替わりでおもてなしします...
電撃座お知らせ 「7月12日はがらくた落語再生工場」
落語家が新作落語に挑戦するも、うまくいかずに途中で捨ててしまったネタがある。それを回収再生するというのが「がらくた落語再生工場」の趣旨だ。個人プレーではなくてトリオで挑戦し、自分の放棄したネタを仲間に完成させてもらうというところにこの落語会の新しさがある。 さらに演者たちは、その一部始終を演劇仕立てにすることを思いついた。噺だけではなく、高座を芝居の舞...
電撃座通信 立川談修「談修アンプラグド #2」20170707
2017年の7月7日は雨の降らない七夕だった。 この日に開催されたのが、落語立川流真打・立川談修さんの「談修アンプラグド ♯2」である。題名からおわかりの通り、電子機器の拡声機能を使わないことを重視する落語会である。落語は筋立てだけを楽しむものではなくて、噺に滲み出てくる演者の人柄が大事な要素になる。それをよく理解してくださっているお客様がこの...
電撃座通信 桂夏丸「夏丸ヒットパレード #4」20170709
祝・桂夏丸さん来春真打昇進決定。 落語芸術協会の二ツ目では香盤が最高になっていたので時間の問題かと思っていたが、先日の理事会で正式決定したとのことである。ご本人にうかがったところ、すでに披露目のパーティー会場も予約し、準備を開始されたとのことだった。今年昇進を果たした昔昔亭桃之助さんに何をすればいいかお聞きしたところ、やらなければいけないこと、...
電撃座通信 おさん&たこ平「ゴールデンバッテリー」20170628
柳家花緑門下の一番弟子・台所おさんさんで最初に聴いたネタは「蒟蒻問答」だったと思う。そのころは二ツ目だったので「台所鬼〆」だった。東京かわら版でぱっと名前を見ても、この人がどこの門下なのか、そもそも落語家なのかどうかもわからない名前である。かわら版に載っているのだから落語家か講談師か浪曲師のはずなのだが、手がかりがない。ネットで検索して花緑一門であることを知...
電撃座通信 「寸志滑稽噺百席 其の三」20170630
2016年に開催された「若い(入門10年未満)おじさん(33歳以上で入門)の会」を通して思っていたことがあった。落語立川流の立川寸志さんは現役二ツ目では上から二番目というこの会の象徴といってもいい存在なのだが、今のうちに滑稽噺のレパートリーを増やしておけば真打になったころにはすごい武器になるだろうな、ということである。亡くなった十世桂文治の「豆屋」とか五代目...