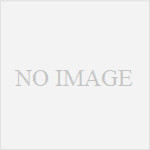大阪行最終日。この日も一心寺門前浪曲寄席はあるのだが、19時から朝日カルチャーセンターのリモート講義が始まるので、どうしてもその前には帰宅していなければならない。そのためには15時には一心寺を出たほうがいい。だがそれだとトリを最後まで聴けるかわからない、ということで残念ながら早めに大阪を出ることにした。いろいろと穣り多かった大阪、ありがとう。
で、選んだのが西成区と阿倍野区の古本屋に行くことだった。すでに鞄は昨日までに買った本でぱんぱんである。最悪の場合は手で持つしかないが、新幹線の発車まで時間があるんだから仕方ない。未訪の店があるんだから、行くしかないではないか。
新今宮駅から阪堺電鉄に乗ろうと思ったのだが、あいにく行ったばかりであった。やむなく堺筋線で天下茶屋まで。そこから南西に少々歩いたところに福永書店岸里店がある。元は複数展開していたのだろうか。店構えは個人経営店そのもので、ずらりと文庫が並べられた店頭の風景は新古書店のような感じだが、中に入ってみると意外に硬派な古本屋なので驚かされる。店内右側の壁際が文庫と文学のゾーンで、左に行くにしたがってコミックなどが多くなっていく。入ってすぐ左にあるガラスケースには本以外のグッズなども並べられているのだが、そうした要素だけで判断すると誤るのである。
文庫棚でまず松本清張『ゼロの焦点』を拾う。これもマライ・メントラインさんとの対談用に再読するつもりである。帰りの新幹線で読もう。それで買えるものを確保して安心し、棚を見返して驚いた。右側の文学列には郷土作家のコーナーが充実しているし、詩集のたぐいもきちんと置いてある。中央のサブカル棚には珍しい芸人本などもあって、瑞々しい雰囲気である。しばらく誰にも荒らされずに保存されていたことがわかる。新雪を踏むような気持ちになる。
すっかり見回って目星をつけた時点でアダルトコーナーに入った。こういうところも一応見るのである。ざっと目を通して、隅になぜかスポーツコーナーがあるのに気づいた。ん、なぜアダルトコーナーに。これが正解で、昭和から平成にかけての女子プロレス関連書籍を山のように発見。ダンプ松本と大森ゆかり(友加里)の引退記念共著『なんたって乙女の底力』(スコラブックス)とか羽佐間聡『翔べJBエンジェルズ』(新政出版局)とか、全日本女子プロレス全盛期の本が山のようにある。長与千種の師匠だった山崎照朝『女子プロレス物語・リングの華闘士』(池田書店)はともかく、志生野温夫『女子プロレス革命伝説―今、語る戦士たちのすべて』(ステディ出版)なんて本は存在すら知らなかった。志生野アナウンサーの著書なんてあったのか。
これは全部買わないといけない本だが、もう鞄に容量がほとんどない。しかし買わないと駄目だろう。
帳場に行って勘定を済ませ、外に出た。鞄を開いて空間のやりくりをする。あっちにこれを詰め、こっちにそれを押し込んで、となんとか大部分は入れたのだが、どうしても2冊だけ収まらない。やむなくそれは、コートの両ポケットに突っ込んだ。全身本で武装しているようなもので、上半身がぎしぎし言うほどに重い。
ここから次の目的地までは2kmもないのだが、電車で乗り継ぐと面倒くさい。いったん北上して動物園前から御堂筋線に乗り、天王寺まで行って阪堺電鉄で下りてこなければならないのだ。しかし東に歩けば乗り換えをしたのと同じくらいの時間で着く。優に二十キロはある荷物を背負って歩かなければならないのだが。
熟慮の結果、歩くことにする。前に進むたびに膝が軋むが、仕方あるまい。うんうん唸りながら歩き、二十分ほどで阪堺電鉄の線路が見えてきた。それを越し、ちょっと北上したところに安倍晴明社がある。
 ここに来るのは初めてではないが、しっかりお参りするのは初めてだ。ちゃんとご挨拶をしてから、さらに東に向かった。東に、東に。十分弱歩いたところで古本大吉堂に到着した。
ここに来るのは初めてではないが、しっかりお参りするのは初めてだ。ちゃんとご挨拶をしてから、さらに東に向かった。東に、東に。十分弱歩いたところで古本大吉堂に到着した。
 大吉堂にも何回目だろうか。前の店舗のときに一回、移転してからも来ている。ここは十代の居場所を作るという目的で始められた店で、奥には自習スペースなど、十代の子たちが気軽に立ち寄れる机などが置かれている。
大吉堂にも何回目だろうか。前の店舗のときに一回、移転してからも来ている。ここは十代の居場所を作るという目的で始められた店で、奥には自習スペースなど、十代の子たちが気軽に立ち寄れる机などが置かれている。
児童書からヤングアダルト、ライトノベルまでジャンルを横断して本が置かれているのが特徴だ。店の中央には大人向けの本の棚もあり、決してこども向けだけではないのだが、十代の読者に本を届けたいという意志がはっきりと見える。じっくりと棚を見させてもらい、結局は均一棚から小沢昭一・神崎宣武『道楽三昧』(岩波新書)を購入した。
勘定をしてもらいながら店主と少々雑談する。十代の読書動向について、勉強になる。店の奥には非売品として、十代が読みたい本を探すためのレファレンスコーナーがある。『名探偵と学ぶミステリ』が完成したら、ぜひそこに置いてください、とお願いして店を出た。
よし、これでし残したことはない。東京に帰ります。また来るぞ大阪。